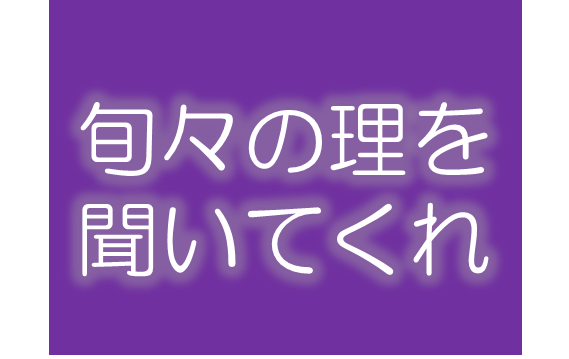一あっての二、何程賢うても、晴天の中でも、日々の雨もあれば、旬々の理を聞いてくれ。聞き分けねば一時道とは言わん。(明治26年12月16日)
一があって二がある。二があって一があるのではない。それはいくら賢い、頭が良いといわれる人でも、その順序をくつがえすことはできない。つまり、人間の知恵や考えだけでは、どうにもならないものがあるということである。
晴天や雨の守護、暖かい寒いということは、人知の支配が及ぶところではない。それに合わせるだけである。また、旬のはたらきもそうであろう。
物ができるには、それぞれ旬がある。お米には、お米ができる気候が必要である。 野菜も同じである。
もし、旬をはずして物をつくろうとすると、そこにはたいへんな労力と費用が必要になる。ハウス栽培のことを考えれば、よく分かるであろう。
私たちの暮らし、営みを考えても、それは同じである。そこには旬というものがあり、ものごとには、順序というものがある。その旬、順序というものを考えなければならない。
天理教では、この道は天然自然の道である、とお聞かせいただくように、この旬、順序というものを、たいへん重要な角目としている。
すなわち、旬にふさわしいように処すれば、事はスムーズに運ぶし、順調なありがたい姿をお見せいただくのである。
その場合、親神様が、ない人間ない世界をはじめかけられ、いまもご守護くだされていればこその人間であり、この世界であることを、ほんとうに心に治めて、ものごとを考えていくことが、順序の根本となる。
いまの旬に思いを致し、親神様によって生かされているという、この順序を心に刻み込んで、勇んで歩んでいくことを願うのである。(安井幹夫、「今日は晴天、今日は雨 おさしづ百の教話集」、天理教道友社)