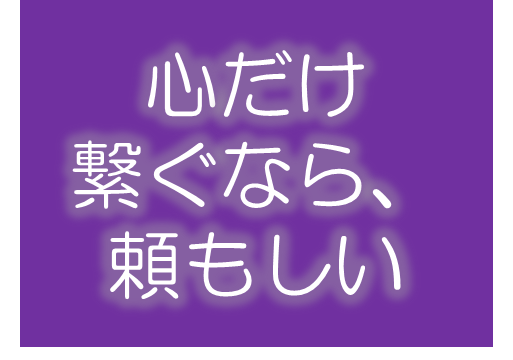兄は兄、弟は弟、互い治まるなら、どんな理も治まる。兄であって身下の理聞かんならん。俺は兄や。兄なら泣く/\の理治めにゃならん、運ばにゃならん。……上やさかいに、下やさかいにと言うても、一つの理強きは随分通れる。なれど心だけ繋ぐなら、頼もしいという。(明治24年12月25日)
家庭には親子、夫婦、兄弟という関係の人間模様がある。その模様は、人それぞれに織りなされる。一軒の家に住んでいても、それぞれの心はみな違う、というお言葉もある。家庭にあっては、お互いの心が治まっていることと、心の繋ぎが大切である。子供たちがみんな元気で健やかに育つには、何よりも家庭がしっかり治まっていなければならない。
こんな当たり前のことが、最近ではなかなか通用しない、という場面に当たることがある。それぞれが自己を主張し、同じ屋根の下に住みながら、家族としてバラバラな家があると感じるのは、私一人ではあるまい。まるで下宿人同士の集まりであるかのような観も、なきにしもあらずである。
変な平等主義がはびこって、訳の分からないことが多い。 やはり、兄は兄として、時に弟の言い分を聞いて、泣きたいようなときでも心を治めることが肝心である。そこにお互いの心の繋がりがあり、頼もしいという姿が現れてくる。
これが家庭の治まりである。家庭に、子供を育てる、一人前にしていくという力がなくなるとき、子供は糸の切れた凧のように、ものごとの判断の基準さえ分からなくなってしまう。 基準、規範の喪失である。
いま一度、何が大切であるか、振り返ってみよう。すべては、心を繋ぐことの大切さに気づくところから始まるのである。(安井幹夫、「今日は晴天、今日は雨 おさしづ百の教話集」、天理教道友社)