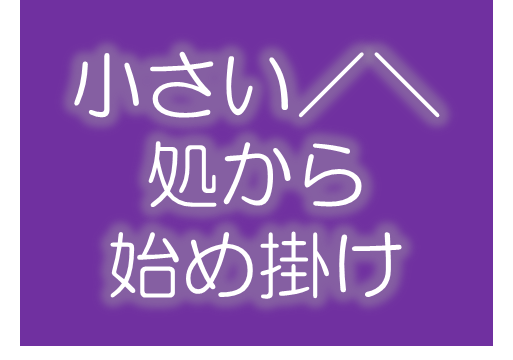何にも無き紋型無き処から、これまでの道成り立ち来た。よう/\聞き分け/\。初めは小さい/\処から始め掛け。心変わらんが一つの理である。……初めは小さき処から/\始めば、どうでもこうでも、こうしようやないか/\と言うて、独り出けて来るのは誠やで。だん/\に出けて来るのは誠やで。これが天理と言うのやで。(明治22年2月15日)
ものごとが成ってくる姿、あるいは、その進め方というものを考えてみるとき、このお言葉が指示するところは重要である。
まず、この道というものが、紋型ないところからはじまったことに思いを寄せ、最初から大きいことをするのでなく、「小さい/\処から始め掛け」といわれる。すなわち、小さいところから始めれば、「こうしようやないか/\と言うて、独り出けて来る」のである、と。しかも「心変わらんが一つの理である」と仰せになって、それを積み重ねていくこと、長く続けることが第一である、といわれている。
皆の気持ちが合わないというのは、そこに無理があるからだと仰せになる。いいかえれば、最初から大きなことをしようとするから、無理をいうことになる。これでは皆の心は、なかなか一つになれない。それは形にこだわるあまり、成ってくる形を求め、大きさとか、立派かどうかということが、成人の到達的目標であるかのような錯覚に陥ってしまうからである。やはり、一人ひとりの心のねりあいを疎かにしてはならない。そこが、ものごとを進めていく原点である。
私たちは、ややもすると結果を焦り、何か大きいことがご守護だと思いがちになるが、そうではない。日々という理が大切である。その積み重ねが、大きなことに成っていくのである。それは、だんだんにできてくる姿であり、「これが天理と言うのやで」といわれる。」とである。(安井幹夫、「今日は晴天、今日は雨 おさしづ百の教話集」、天理教道友社)