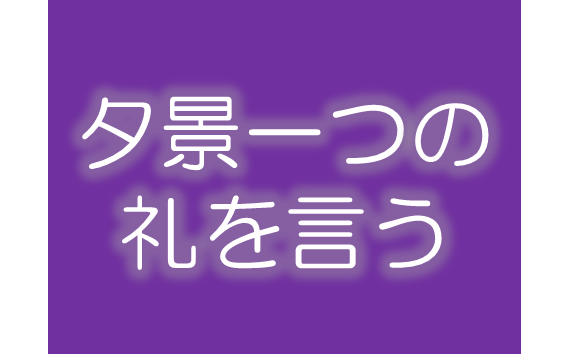心では十分たんのうの理は治めて居る。尽す一つ、運ぶ一つの事情に、理が治まらにゃならん。十分たんのうして、夕景一つの礼を言う。(明治25年7月27日)
日々を暮らす中に、時として山があり、谷もある。また、事情に見舞われて、心いずませて、どうにもならないこともあろう。
そうであっても、心を取り直し、ものごとに取り組んでいくのである。その場合、大事なことは、この道の話を聞かせていただいている者として、たんのうの心を治めて通ることである。
たんのうとは、十分満足する、の意である。満足とは、ふつうには、ものごとが自分の思うように成ってきたことに対する気持ちである。ところが、この道では、つらい苦しいときにも「たんのう」しなさいといわれる。けれども、それを喜ぶことなど難しい。そこに、我慢する、というような意味で捉えられることも多い。
しかし、そのような意味に捉えては、このお言葉は違ったものになる。やはり、たんのうは満足する心持ちなのである。しかも、日々に尽くし運ぶことの中にも、理(この世と身体は親神様のご守護の世界である)が心に治まっていることが大切であるといわれる。このことを案外忘れがちである。
いくら心を尽くしても、運んでも、理が治まっていないと、ややもすれば、これだけこうしているのに、ああもしているのにと、やるせない心が残るかもしれない。それでは、せっかくのつくしはこびも、泡と消えてしまうことになりかねない。 そこに、真にたんのうするか、我慢に終わってしまうかの差が出てくる。
一日を終えて、ああ、今日も結構に暮らさせていただいた、月日・親神様のご守護あればこそと、夕景にお礼を申し上げるところから、真のたんのうができていくのであろう。(安井幹夫、「今日は晴天、今日は雨 おさしづ百の教話集」、天理教道友社)