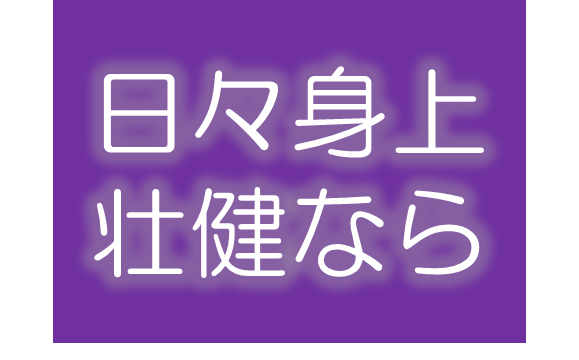さあ/\心に掛かりてはならん。心に掛かりて、心に楽しみあらせん。何程物沢山あったて、心に掛かりて楽しみあらせん。浮かむ日無い/\。何程沢山あったて、楽しみ無い。日々身上壮健なら、何不自由でも不足は無い。(明治34年7月15日)
日々の暮らしの中で、何か心に掛かることがあれば、どんなに面白おかしいことがあっても、心の底から楽しめるものではない。
そうした経験は誰しも持っているであろう。たとえば、家族の誰かが病気になると、家の中は暗く沈んでしまう。子供が大きな病気にでもなれば、たいへんだ。会社にいても気になるだろうし、いつもの付き合いも断って、早々と家路につくことになる。また、受験生をかかえる家庭も、何かと気苦労が多い。家族で旅行を、と思っても、子供が受験だから控えておこう、ということになりやすい。
いかにお金や物があっても、そうした気分はほぐれない。つまり、お金や物で解決することはできないのである。このような場合、健康で元気に暮らしをさせていただいていることが、どれほどありがたいことか、ということに思いを寄せることが大事である。そこに不足の心は霧消してしまうであろう。親神様は、「日々身上壮健なら、何不自由でも不足は無い」と仰せになる。
ものごとは、そうそう思うようになるものではない。それを不足するよりも、物がなくても健康であることを喜び、感謝することである。もし、思うことが思うようになったとしたら、一時は面白いかもしれないが、いずれそのことにも飽きて、 喜びが感じられなくなるだろう。
要は、「成っても成らいでも」の心をもつとともに、ものごとに全力を尽くす。 あとは親神様のご守護を待つことである。その中に成ってきたことを、そのまま受け入れる。これが大切である。これが、ほんとうの喜びである。(安井幹夫、「今日は晴天、今日は雨 おさしづ百の教話集」、天理教道友社)