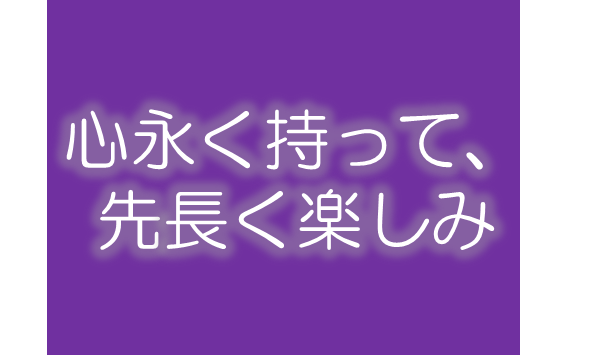これまで長らえて事情、又一つめん/\思わく一つ理更に立てた処が、成るものやない。よう聞き分け。先々永く心持って、何も聞き分け。治めにゃならん/\/\。一時楽しんで了た分にはならん/\。…心永く持って、先長く楽しみ。これ一つ早く治めてくれるよう。(明治27年1月17日)
人間というものは、毎日を振り返ってみると、朝、目を覚まして食事。会社、学校、仕事に出かける。あるいは家事など。 帰ってきて就寝。いうならば、そう大きな変化があるわけではない。同じことの繰り返しが日々なのである。
大きな変化が連続したならば、とてもやっていけるものではない。今日は子供が身上や、お父さんの交通事故だ。明日は葬式だ、結婚式だ、離婚だと、いろんなことが立て続けに起こってくる毎日だとしたら、どうであろう。変化がないのが、ある意味ではありがたいのである。
ところが、そうした生活が続くと変化を求めるのが、これまた人の常でもある。ほかに何かいいことがないかしら、と思ってしまうのである。
教会でつとめる、あるいは信仰している道中においても、そんなことを思ったりしやすい。こんなことをしていて、何になるのかと思ってしまう。あれこれと思惑をしてみたところで、それは成る話ではない。何ごとも親神様の思惑を忘れては、成ることも成らなくなってしまう。
一時の楽しみに心を奪われては、どうにもならない。親神様の思惑のままに、こんなこと何になるのか、というような道中こそが大切なのである。
親神様の思惑は、今日や明日のことだけをいわれるのではない。将来を見通して、今日どうあるべきかを教えてくだされている。だから、「心永く持って、先長く楽しみ」といわれるのである。コツコツと先を楽しんで歩ませていただこう。(安井幹夫、「今日は晴天、今日は雨 おさしづ百の教話集」、天理教道友社)