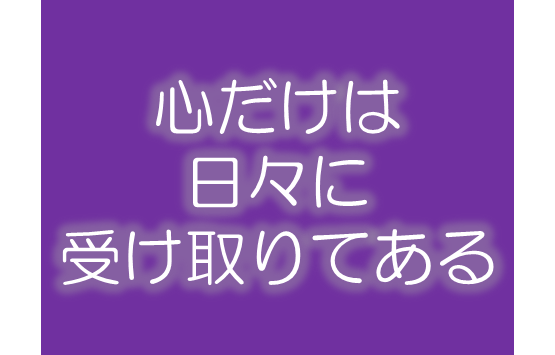これから先思う事直ぐに出る、直ぐに見える。一名一人の心だけは日々に受け取りてある。よう聞き分けて互い/\の暮らし合い/\、互い/\知らし合いすれば、たヾ一つの諭、一つの心で日々遊山な心で通れる。(明治26年5月18日)
お道を通らせていただいているお互いとして、一番に心しなければならないことは、やはり日々の心のあり方である。形は同じように見えたとしても、その心のあり方が違っていては、成ってくる姿が違うのである。
もちろん、形も大事なことに違いはない。私たちは、いくら心をつくれと仰せいただいても、どうしたら心がつくれるのか、大いに悩むところである。したがって、そうしたときには、まず形からつとめることが大切となる。
いわば、形を通して心を学び、その心を通して、さらなる形の充実をめざし、そこからまた一段と深い心にならせていただくのである。 そうした繰り返しの中で、心のあり方を親神様に受け取っていただくのである。
そこに、思うことがすぐに見えてくるようになる、とまで仰せくだされる。もちろん、心が違えば、わが思い通りの、都合のよいことだけが見えてくることにはならない。まさに、形ではなく、心通りの守護である。
暮らしの中で一つの心があれば、遊山な心で通れる、と教えられる。陽気に明るく暮らしたいというのは、みんなの願いである。それにはまず、陽気ぐらしをさせてやりたいと思召しくださる親神様の心に、自らを合わせていくということがなければならない。合わせるということは、元初まりにおいてと同様に、親神様に食べて味わっていただくことである。そこに、いったん無となった自らが、新たに生かされる道がひらけてくる。そうした日々の心が大切である。(安井幹夫、「今日は晴天、今日は雨 おさしづ百の教話集」、天理教道友社)