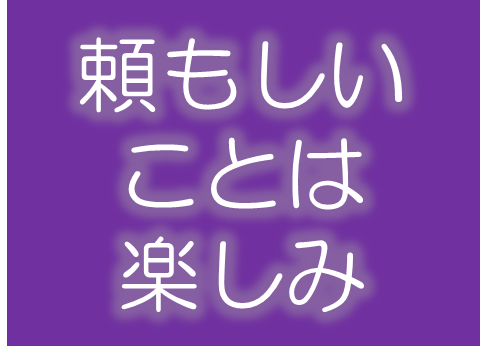年限という、不自由な日もあれば、頼もしい日もある。…遠慮気兼ねは要らん。辛いものは辛い、甘いものは甘いと持てば同じ治まる。頼もしい事というは楽しみという。(明治25・12・28)
諸井政一という方は、山名大教会の初代、諸井国三郎先生の長男であり、小さいころからおぢばで育ち、将来を楽しみにされた俊才であったのですが、早く出直してしまい、惜しまれた人です。『正文遺韻』という本を残しました。
僕は修養科一期講師の時、山名の諸井慶一郎会長さんと一緒でしたので、いろいろお話を聞く機会がありました。「諸井家には、長生きする人と早死にする人とが交互にやってくるのです」とおっしゃっていました。慶一郎会長さんのお父さんは、慶徳とおっしゃり、東大を出て文学博士となり、やはりその俊才を楽しみにされた人でしたが、四十六歳で出直されました。『諸井慶徳著作集』という本が出ています。
長い間には、天気でも晴れがあれば雨もあり、いろいろな日があります。お道とて同じことです。だから、「遠慮気兼ねは要らん」とおっしゃっています。お道に遠慮はほこりとなっています。神様と人間は親子の間柄なのだからでしょう。
高慢もいけないが、遠慮し過ぎも高慢の一つと言われます。でしゃばり高慢と引っ込み高慢とを比べたら、引っ込み高慢のほうがよけいいけないそうです。
何かにとらわれたら不自由となります。自由とはとらわれぬ心ですね。天気が良くても結構、悪くても結構、晴れも結構雨も結構という心、その心が頼もしい心であり、楽しみとなります。
苦しい時、どん底の時も、得意の絶頂の時も、何ものにもとらわれぬ心、変わらぬ心、この心こそ頼もしい心ですね。変わらぬが誠、であります。良くても悪くても、変わらず真実誠の種をまいていけば、やがて必ず芽を出し、花が咲き、実る日が来るものです。
悪いんねんの種もまた実ってくるので、こちらは早く刈り取る必要があります。実る前に刈り取りせぬと、種が落ちてしまって何層倍の苦労になります。
たとえ一日一粒でもしっかり良い種をまき、悪い種の刈り取りも一日一本なりと心がけたら、一年たてば三百六十五本になり、十年たてば三千六百五十本になります。
元東大総長が一日一善の親切運動を提唱したことがありましたが、一年三百六十五日欠かさず続けることができたら、その内容の如何よりも別の価値も生じますね。続けるということは本当に素晴らしいことですね。
お道のご用は人徳に勝る天徳を頂ける道でもあるので、楽しみが一段と深まります。陰の徳積みほど先が楽しみです。今は、人間万事金の世の中のように見えても、金の力だけではどうすることもできないことがいっぱいあります。徳のある人々にはかないませんね。
長い間には良い日も悪い日もあります。そのどれをも楽しんで、むしろ難儀が結構、苦労が財産と受け取って、良くない日ほど楽しんで通れるようにならせていただくことです。(渡部与次郎、「続おさしづに学ぶ – 朝席のお話」、天理教道友社)