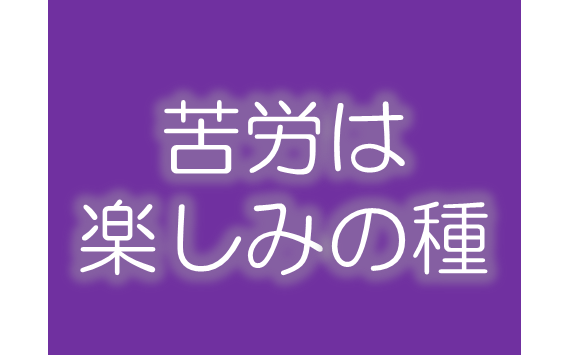成らん時を思い出せばたんのう/\。先は神が引き受けて居る。案じる事要らん/\。よう聞き分け。難儀さそう不自由さそうは無い。どうせえこうせえあろまい。よう聞き分け。どんな事も勇んでくれるよう/\。…苦労は楽しみの種。どうでもこうでも楽しみ働けば、これ種と成る。…旬という、時旬という、急いだ処が成るものやない。旬という、時という、独り出けて来るは旬と言う。(明治33・12・22)
旬にかなって楽しんでかかれば、一粒万倍の理が頂けます。初め楽しめなくても、工夫し、努力して、楽しめるようになることが必要です。楽しまないと、一生懸命やっても一粒万倍にはなりません。
しかし、いくら一生懸命楽しんでやっても、旬を外せば成ってきません。鉄は熱いうちに打て、と言いますが、自分にかまけているうちに冷えて固くなったら、打っても無駄になります。
河原町大教会の初代は“結構源さん”と言われた人で、鍛冶屋をしていました。真っ赤に焼けた鉄屑が目に飛び込んだ時、「無い世界無い人間をこしらえた親神様なら、この目の一つや二つおたすけくだされんことはありますまい。この目をたすけていただいたら、たとえ火攻め水攻めに遭おうとも、生涯ご恩報じをさせていただきます」と誓って、見事不思議なご守護を頂いたのでした。
このご恩返しの心が強い人ほど良くなっていくなあと思います。これがたすかる人の心だなあと思います。
河原町からは三十を超える大教会が分離しています。一切を上手に、結構結構と喜んで受ける心、これがその栄の根本なのでしょうね。(渡部与次郎、「続おさしづに学ぶ – 朝席のお話」、天理教道友社)