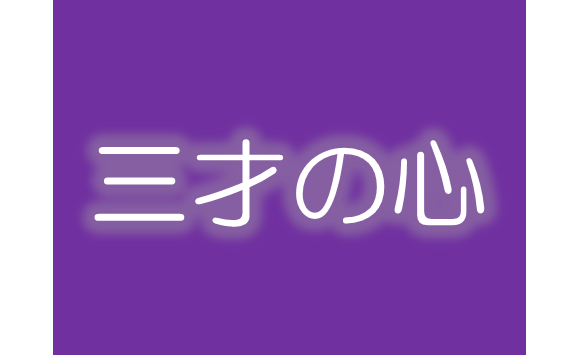小人という、小人一つの心なれば、小人三才の心というものは、何にも心に掛けんものや。(明治22・11・7)
みかぐらうたでは、「三に さんざいこヽろをさだめ」(一下り目)と濁りますので、「三才」ではなく「散財」ではないかという意見もあるようです。散財する時は惜しげもなく楽しんで使いますので、心に掛けないところが三歳の心と似ていることから、そんな意見も出るのでしょうね。
天理教少年会から『さんさい』という月刊誌が出ています。若い母親向けの編集にしていて、なかなか子供の教育の上に役立つ内容なので、愛与布教所の信者さんもかなりの人が購読しています。
持たせれば持ち、持たさねば持たんという無邪気な三才心。ほしいとも思わんがいらんとも言わん、素直で心にちっとも掛けないというところが、大人の皆さんが見習うべきところなのでしょうね。
大人の中には、殊にお道を聞いて二十年も三十年もたっている人でも、三歳の子供にも劣る心の人がいますね。その人も三歳のころは同じ心であっただろうに、その点に関しては、心の成人どころが退歩していることになりますね。
三歳児は、母親にもたれ切って、まかせ切っているからこそ、何にも心に掛かけずにすむのですから、われわれも親なる神様にもたれ切って、まかせ切って通らせていただくことですね。(渡部与次郎、「続おさしづに学ぶ – 朝席のお話」、天理教道友社)