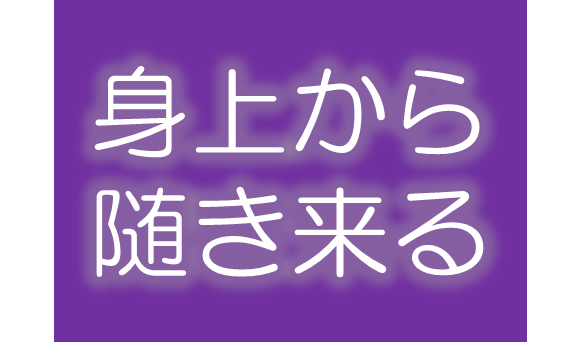この道は皆身上から随き来る。身上でなくして随いた者は、ほんの一花のようなもの。(明治33・11・26)
身上で道についた者でないと、かしもの・かりものの理がよく分からないし、これが分からないとお道の一切が何一つ分からないのと同様なので、ほんの一時の花のようなことになりやすいのですね。
身上のおさしづで多いのは、これだけやっているのにと思ってはいけない、たんのうの心を治めるように、というものです。たんのうはいんねんの自覚ができないとできないものですが、かしもの・かりものの理と深くかかわっていますね。
身上の危ないことを事情で教えられることもあります。自分が身上病まずとも、他人様の身上だすけによって、かしもの・かりものの理をしっかり承知させていただけば、ほんの一時の花のようなことにならぬかもしれません。(渡部与次郎、「続おさしづに学ぶ – 朝席のお話」、天理教道友社)