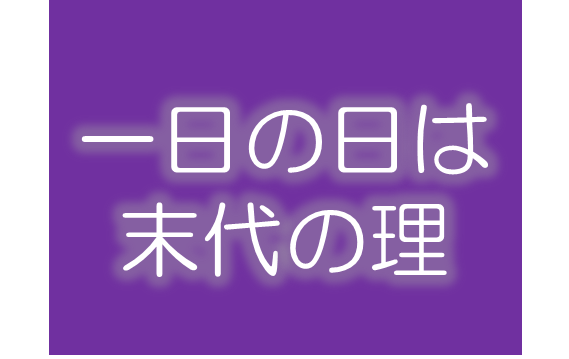人を救ける道なら、救かるは天の理である。日々の理である。…一日の日は末代の理も同じ事。さあ/\定め理は、楽しみ/\と定め。天より一つ道一日の日ある。難儀さそう、不自由さそうという親は世に無い。この理治めてくれるが楽しみという。(明治34・11・4)
一日一日がつながって一生となり、その一生がまた生まれかわって末代に及ぶのだから、「一日の日は末代の理も同じ事」とおっしゃっています。一日生涯の心で一日一日を通るだけでなく、この一日が末代につながると思って生きていくなら、それを楽しめるなら、素晴らしい生き方と言えるでしょうね。
親神様の心になり、その親の思いを人々に伝える人が一人でも多くなることを、親神様はどんなに楽しみにお待ちになっていることか、よく分かりますね。親が楽しむのを楽しんで、一日一日を楽しみに通れるようにならねばいけませんね。「楽しみ/\と定め」と仰せになっています。
愛街の初代会長様は、毎日夜の十二時になると、「神様、関根は今日、このくらいでよろしかったでしょうか。満足してくださったでしょうか」と、お伺いなさったのでした。こうした一日一日の欠かすことのない積み重ねが種となって、今日の愛町分教会となっているのですね。
初代会長様は、教会づとめの合間を縫って、毎日何軒となくおたすけに回られたようです。皆さんも、少なくても一日一度はおたすけに出ることですよ。
ひのきしんで泥まみれになっても、おたすけ先でひどい目に遭っても、心は晴れ晴れとしますね。特に、たすかっていただく喜びは、たすけられた喜びより何倍も大きいものですね。楽しみはそこから出るのが一番でしょうね。
苦労すればするほど人はたすかってくださるので、苦労が楽しみになってきます。さあ、おたすけに急き込んでください。(渡部与次郎、「続おさしづに学ぶ – 朝席のお話」、天理教道友社)