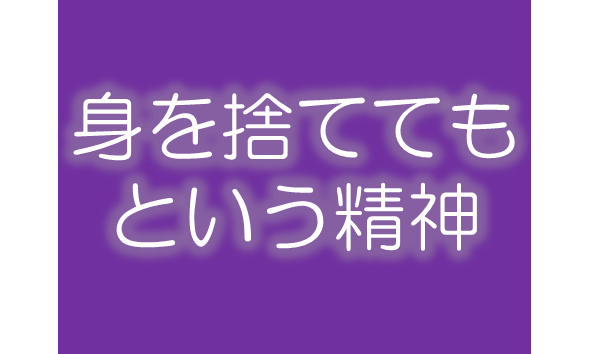何ぼどういう事を言うたて、言うのが悪いなあ、言うてはいかんなあ。包んで居ては真実真の事とは言わん。我が身捨てヽも構わん。実を捨てヽもという精神持って働くなら、神が働く、という理を、精神一つの理に授けよう。(明治32・11・3)
言っても何倍にはね返ってくる、仇を取られる、だから言わないでおこう、というのもいけないのですね。「我が見捨てヽも構わん」という心、この心に神様が乗って、足りないところは足してくださるのですね。
愛町の初代会長様は若いころ、あるおたすけ先で「三日でたすかる」と言い切ったところ、「もしたすからなかったらどうするんだ」と聞かれ、「腹を切ります」と答えました。ところが三日目になってもたすからないので、「たすからんじゃないか」と問い詰められ、「今夜の十二時までが三日ですから、それまでお待ちください」と答えたものの、心の中では”腹を切らねば”という思いを持たれたのでした。
それで、短刀を月の光で研いで、”人だすけのために命を落とすなら本望”と覚悟を定め、翌朝その家を訪ねると、その覚悟を定めた時間から病人が良くなって、朝は起き上がって迎えたとのことでした。
「医者の手余り捨てもの救けるが、神のたすけと言う」(明治29・5・1)というお言葉もあります。そんな人を探しておたすけさせていただくことが大切です。そんな人をたすけるには、捨て身の精神が必要です。そんなおたすけの中に神様が見えてくるのですね。不思議不思議と成ってくるのですね。(渡部与次郎、「続おさしづに学ぶ – 朝席のお話」、天理教道友社)